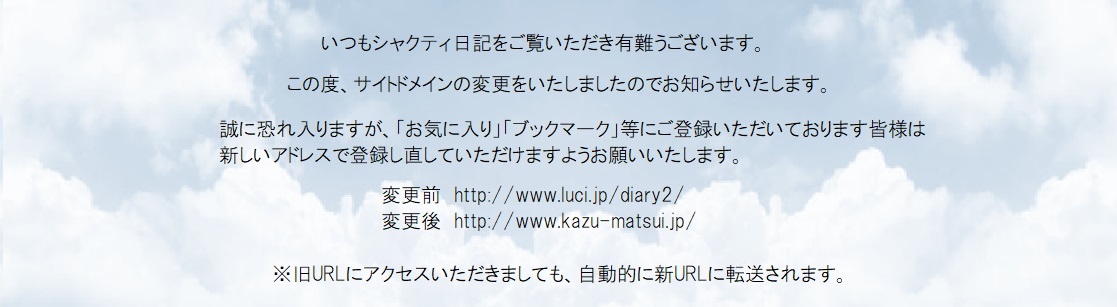「光りの子どもの家」の菅原哲男氏の本から、もう少し
家庭型養護施設「光りの子どもの家」の菅原哲男氏の著書「誰がこの子を受けとめるのか」:この本を読んでいると、主観的に「子育て」を捉えなおす指針になる。子育てを仕組み(保育、教育、施設、福祉)の中で考え、待機児童、学力、少子高齢化、年金、税収といった数字を元に施策が進められようとしている時に、「育ち」の意味を、もう一度、仕組みの中でさえも原点に戻し、一個人の人生とそれに関わる人たちそれぞれの思いとして伝えようとしている。
保育界が保育士不足と市場原理に追い詰められ、その質、というか、育てる側の心の健康を保つのが年々困難になってきているいま、施設や仕組みによる「子育て」の難しさと限界を知る意味で、忘れてはならない視点、重い証言だと思うのです。
親が親らしさを失いつつある現状では、親身になると保育士が精神的にもたない、でも、親身にならないと、見えないところで仕組みの本質が崩壊してゆく。(北欧で、国民が傷害事件の被害者になる確率が日本の20倍。)
202頁に「子どもと関わる」という章があります。
三才までの人生を乳児院で育った子と、いい環境とは言えなくても乳児期に家で親に育てられた子が家庭型養護施設で育てられ高校生になり、乳児と関わった時の実話と菅原先生の考察が綴られています。
それを読んでいると、三歳未満児の保育園での保育を雇用労働施策の一環として安易に奨励する国の施策が恐ろしくなってくるのです。保育園児は毎日家に帰ります。乳児院や養護施設のように日々の生活が親と離れている環境とは異なります。でも、そこで行われる「子育て」の限界、その意味や意図、理由が似ている。これだけ長時間、しかも乳児から預かれば、保育園は家庭の役割を果たさなければならない。しかし、何か遺伝子の中に深く組み込まれている、人間が社会というパズルを組むときの隠された法則のようなものが、「光りの子どもの家」の試行錯誤、その限界の中に垣間見える。
人間にとって、乳幼児期に愛着関係や独占欲を満たされないことがいかに決定的か。それが決定的であることが見えにくいから、「光りの子どもの家」からの証言が重要な原点になってくる。数年前に、当時の厚労大臣が「子育ては専門家に任せておけばいいのよ」と言った発言が対極に見えてくる。
「専門家」が言う、専門家という言葉に騙されてはいけない。彼らの思考の中には、菅原さんが書くような決定的瞬間は一瞬たりとも存在していない。
菅原さんが、その章で書いたことを要約します。
三才まで乳児院で育った世話好きな高校生亜紀は、乳児の由紀が可愛くて仕方ない。その亜紀がある日自分の部屋で哺乳瓶にジュースを入れて飲んでいた。少ない小遣いから哺乳瓶を買って一人で飲んでいた。そして、同じように乳児院で育った高校三年生の嬉は、食欲が落ちてゆき、ある日、保母にリンゴをすってくれと頼む。保母にそうしてもらっている乳児が羨ましかったのでしょう。そして、一歳半の乳児がこの二人には寄り付かない。三歳まで親に育てられた高校生には懐くのに、この二人には懐かない。疑似家族のような関係の中で、施設に入所する以前の乳幼児期の体験の差が「育てる側の立場になった時に」浮き彫りになる。
菅原さんが書く、乳児期の「個別的継続的な養育者との関係」の欠如が高校生になっても、人間関係、特に幼児との関係に深い影響を与えている光景を知ると、政府が積極的に3歳未満児を保育園に預けることを奨励することの危険性をひしひしと感じます。
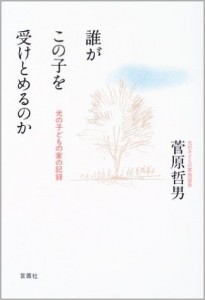
(2014年、4年連続で減っていた「二万一三七一人の待機児童」を解消するために、「40万人の保育の受け皿を確保する」と政府が言った。そして、減らしても減らしても、政府の意図と親の意識の変化に沿うように、待機児童は増えている。政府の意図がいつか修正されても、親の意識がマスコミの報道によって連鎖し始めた時、それはもはや修正できないのではないか。乳幼児期の保育は「個別的継続的」関係ではありません。保育士との比率は1:3か1:6。そして複数担任。しかも半年、一年で担当保育士が変わる。加えて、施策に追い詰められた園長が保育士に、乳児を抱っこするな、話しかけるな、と指導する保育さえ現れているのです。http://kazu-matsui.jp/diary2/?p=779)

個々の人生には、それぞれ異なる出会いがある。育ちあいの可能性は確かに無限です。幼児期にこういう育ちかたをしたから人生が必ずこうなる、ということはない。しかし、イジメや不登校、教師や保育士の職場離脱、一般の職場でも三年続かない新入社員が増えていることなど、「育てあい」「育ちあう」人間の営みが、親身になる機会を奪われ、悲鳴を上げ始めている。問題は多岐にわたっていますが、男たちが結婚しなくなったことも含め、社会に自然治癒力や自浄作用が働かなくなっている。この国でも、欧米の後を追うように家庭崩壊が加速し、社会の空気が荒れ始めているのは、多くの人たちがすでに感じていることだと思うのです。その原因は、全般的な幼児期の愛着関係の不足にあるのではないか。「光りの子どもの家」からの証言が、そう語りかけてくるのです。その原因は、全般的に、「幼児を眺める時間」が不足しているからではないか、と私も思うのです。
保育士養成校の先生がこんなことを言っていました。
「以前は、誰かを幸せにしたいと保育科に学生が来たが、今は、自分が幸せになりたくて保育科に来る」
子ども相手なら幸せになれるかもしれない、と思って来ても、子どもが言うことを聞いてくれないとイライラし、すぐに不幸を感じてしまう。予測する力、想像力が欠けているから、どうしていいかわからなくなる。子どもを幸せにすることで幸せになる、というもっと深い、古の伝統的幸福感が欠けてきている。「育てる側の思い」が逆転し始めている。
3歳未満児保育をなくせというのではありません。もういまの社会には必要だから、そして、親に任せておくと子どもが危ないから、乳児院さえ存在する。しかし、幼児期の母子分離がどういうことなのか、フロイトやユニセフの白書を読まずとも、社会全体で常識として把握していないと、このまま進めば社会で補う限界はすぐに来る。

イジメや体罰の問題にしても、憎しみは、愛され満たされたいという飢餓感と表裏一体です。孤独感が往々にして「他の幸せを許せない」という行動につながる。そして、同年齢の子どもたちが不自然に集められている学校という仕組みの中で、互いに抑えが利かない状況にまで進む。教師たちがその子たちを愛し、世話し、その飢餓感に応えるには限界がある。しかしその努力をしないと授業が成り立たない。教師は、もう逃げ出してもいい、とさえ思います。その方がいいのかもしれない。
学校へ入学する前に、親たちをそこそこ親らしくするしか学校が成り立つ道はない。保育は子育てであって「サービス」ではない、ということを政府と行政が親たちに宣言し、親たちの人間性や育ちを保育者たちが日々の出会いの中で見極め、いくつかの義務と責任を課してゆく。卒園後も続くような親たち同士の絆を、保育園・幼稚園を中心に作ってゆく。こうしたことをすぐにでも始めないと、今の状況下で育った子どもたちがどんどん社会の不良債権になってゆくのです。もう、時間がない。
母親の涙
私立の保育園で講演しました。講演が終わって、空っぽになった保育室で一人の母親から相談を受けました。子どもが言うことをきかない、と言って泣いています。聴くと、園ではいい子で大丈夫。家で、お母さんと一緒になると我がままになる、まとわりついて離れない。色々尋ねると、父親は、いい親らしいのです。
「あなたはいい母親だから、子どもが一緒にいたいんです。仕事を辞めることは出来ないのですか?」とたずねると、看護士ですからいま辞めても、また復帰することはできます、生活に困っているわけではないです、と言います。
遠慮していたのか、部屋から出ていた父親が問題の2歳の男の子を抱っこして近づいてきます。父親にしがみついているその子を見て確信しました。なぜ、母親が泣いていたのか。母親も、息子と一緒にいたかったのです。
「いい機会でしたね。2年くらいでいいですから、一緒にいてあげて下さい。今日ここで私に質問したのが運命だと思って。この園を辞めても、子どもをおぶって園に手伝いに来てください。この子を知っている人たちと縁を切らないように。もうその人たちはこの子の財産ですから」
それを聴きながら、父親が少し笑顔になります。
園長先生にあとで、「どんな質問でしたか?」ときかれ、その会話を伝えると、園長先生が本当に嬉しそうな顔をしました。